|
|
〔裂肛・切れ痔〕 |
|
消化器官の最終部分は大腸ですが、大腸は盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸、そして最後に肛門へと繋がっています。 |
|
|
「痔核」とは「いぼ痔」のことで、直腸や肛門周囲に静脈密集部分がうっ血し膨れたものです。直腸と肛門の内外の位置により、内痔核、外痔核と呼ばれます。痔核は肛門部の静脈に負担がかかると起こります。 |
|
|
〔裂肛・切れ痔〕 |
|
消化器官の最終部分は大腸ですが、大腸は盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸、そして最後に肛門へと繋がっています。 |
|
|
「痔核」とは「いぼ痔」のことで、直腸や肛門周囲に静脈密集部分がうっ血し膨れたものです。直腸と肛門の内外の位置により、内痔核、外痔核と呼ばれます。痔核は肛門部の静脈に負担がかかると起こります。 |
|
|
◆〔裂肛・切れ痔〕とは、一体どんな病気なのかご説明します。 |
| 肛門の構造 |
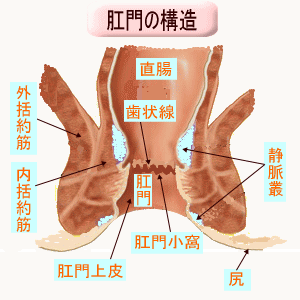 肛門は、消化器官の最終部分にある器官です。肛門はデリケートな器官で、長さは約3cmあります。肛門の周囲は、「内肛門括約筋」と「外肛門括約筋」という二つの筋肉が取り囲んでいます。これらは排便時以外は閉じていて、肛門から便が漏れ出ることはありません。
肛門は、消化器官の最終部分にある器官です。肛門はデリケートな器官で、長さは約3cmあります。肛門の周囲は、「内肛門括約筋」と「外肛門括約筋」という二つの筋肉が取り囲んでいます。これらは排便時以外は閉じていて、肛門から便が漏れ出ることはありません。肛門粘膜の近くにある内肛門括約筋は、不随意筋で、自律神経によって支配されていて、本人の意思とは関係なく肛門を一定の力で締め付けていて、眠っているときでも便が漏れたりはしません。 一方、外肛門括約筋は、随意筋で、脊髄神経に支配されていて、本人の意思で緩めたり、締めたりすることができます。急に便意をもよおしても我慢できるのは、この筋肉のお陰です。 直前の結腸で水分を吸収された便が直腸へ降りてきて、直腸が拡げられると、自律神経の反射作用で便意が起こります。本人が排便したいと思うと、外肛門括約筋が緩んで、排便できるようになります。 直腸と肛門部の接合部は、肛門のふちより約1.5cm奥の方にあり、歯のようにギザギザ状なので歯状線とよばれています。この歯状線の奥側は自律神経の支配下にあり、異常があってもほとんど痛みは感じません。歯状線より、お尻に近い外側部分は、皮膚と同様に脊髄神経(体性神経)の支配下にあるので、異常があれば敏感に痛みを感じます。 |
|---|---|
| 切れ痔はどんな病気ですか? |
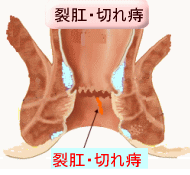 痔は肛門部および、肛門付近にできる病態であり、二つの異なる神経系の支配下にあるために、痔の発症部位によって、痛みの症状は異なります。
痔は肛門部および、肛門付近にできる病態であり、二つの異なる神経系の支配下にあるために、痔の発症部位によって、痛みの症状は異なります。痔の種類には「裂肛(切れ痔)」「痔核(いぼ痔)」および「痔ろう(あな痔)」の三種類がありますが、裂肛・切れ痔は肛門の左図のような部位が裂けてしまった状態をいいます。 |
|
|
◆〔裂肛・切れ痔〕の症状をご説明します。 |
| 裂肛・切れ痔の症状 |
肛門出口から1.5cmほど内部に入ったところは皮膚に似た上皮で覆われていて、通常、肛門と呼ばれていますが、この部分にできた傷を「裂肛」あるいは「切れ痔」といいます。 |
|---|
|
|
◆〔裂肛・切れ痔〕の原因や発症の仕組みをご説明します。 |
| 裂肛・切れ痔の原因 |
痔の大部分を占める痔核の原因は、便秘などで頻繁に力んだりして肛門に負担を掛けることで起こります。女性の場合で妊娠後期で子宮が左右の腸骨静脈を圧迫して分娩時に力むと内痔核になることがあります。 |
|---|
|
|
◆〔裂肛・切れ痔〕の検査方法や診断方法をご説明します。 |
| 裂肛・切れ痔の診断 |
通常、痔の検査は「触診」で行われます。横向きに寝て、膝を曲げ、医師に対してお尻を突き出した格好をします。医師が薄手の手袋をして、肛門に指を入れてグリグリします。これで大体のことは分かります。全裸になるわけではないので恥ずかしいということもありません。 |
|---|
|
|
◆〔裂肛・切れ痔〕の治療方法をご説明します。 |
| 治療方針 |
裂肛・切れ痔の治療法は、切れ痔が起こる原因によって異なります。原因を見極めた上で正しい治療法を行う必要があります。最大のポイントは原因の除去ですが、現実的にはそれも困難なことが多いので、軟膏などの医薬を用いたり、外科手術により治療することになります。 |
|---|---|
| 原因の除去 |
切れ痔の原因が便秘である場合、便秘の改善が不可欠です。適度な運動や食物繊維の摂取、十分な水分の補給で改善することもあります。必要なら、下剤を使用しますが、強すぎて下痢にならないようはものでないといけません。便はある程度の硬さが残る状態が好ましいです。 |
| 軟膏などでの治療 |
初期の切れ痔であれば、その原因である便秘や下痢を改善できれば、かなり改善されますが、軟膏などの塗り薬を併用すればなおよいでしょう。 |
| 外科手術療法 |
切れ痔が重症になり、潰瘍やポリープができてしまったときや、医師による治療を続けても症状が改善しないときは、最後の手段として外科手術が必要となります。あまり長期間にわたって放置すると厄介な「痔ろう」に発展してしまうこともあるので注意が必要です。 |