|
|
〔O脚〕 |
|
両足のくるぶしをくっつけたとき、下肢が外側に凸に湾脚した状態を「内反膝(ないはんしつ)」と呼びます。 |
|
|
|
〔O脚〕 |
|
両足のくるぶしをくっつけたとき、下肢が外側に凸に湾脚した状態を「内反膝(ないはんしつ)」と呼びます。 |
|
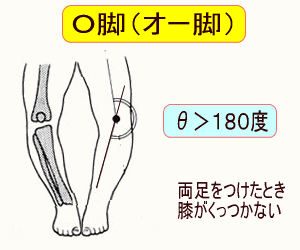
|
通常、生後1年くらいまでの乳児では、生理的に軽度のO脚となっていますが、これが高度な場合は病的なO脚とされます。 O脚とは反対の症状に 〔X脚〕 というのもあります。 どちらの場合とも、骨盤を支えている関節や筋肉に歪みが起こっているのが原因とされますが、それ以上に、日常動作がそのような歪みを生じさせていることも多いとされます。 |
|
|
◆〔O脚〕とは、一体どんな病気なのかご説明します。 |
| どんな病気ですか? |
普通なら、左右両足のくるぶしをくっつけて起立すると、両足の膝が互いにくっつく状態となります。しかし、両方のくるぶしをくっつけると、両足の関節が開いてしまい、膝がくっつかい状態の人や、逆に両膝をくっつけても、両足のくるぶしがくっつかずに離れてしまう人もいます。 |
|---|
|
|
◆〔O脚〕の症状をご説明します。 |
| O脚の症状 |
O脚やX脚は、特別に重大な病気ということではありませんが、見た目には足を揃えて立つことができないので、あまり美しいとはいえないかも知れません。また、あまり程度が激しい場合には、腰や膝に負担がかかってしまい、身体の他の部分に影響がでることがあります。 |
|---|
|
|
◆〔O脚〕の原因や発症の仕組みをご説明します。 |
| O脚の原因 |
歩行を開始したばかりの新生児の歩き方に異常がでる場合があります。一般に新生児は2歳くらいまではO脚傾向になるのですが、それ以降は急速に改善して、3~4歳頃には正常になるか、少しX脚の傾向になります。これは程度の差はあっても、誰もが辿る一種の生理的パターンとされます。 |
|---|
|
|
◆〔O脚〕の検査方法や診断方法をご説明します。 |
| O脚の診断 |
病的な原因があって、O脚になっている場合には、原因に対応した治療が必要となりますが、治療を受ける必要があるかどうかの最初の判断は次のようにするのが好ましいです。
|
|---|
|
|
◆〔O脚〕の治療方法をご説明します。 |
| O脚の治療 |
乳幼児の生理的なO脚であれば、成長とともに自然に矯正されますが、筋力の弱い人の場合、骨格が正常に成長しないことがあります。骨が弱いと自分の体重を支えきれずに骨格が歪むこともあり、O脚の原因となります。 |
|---|