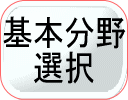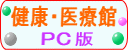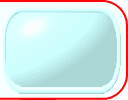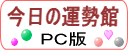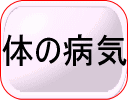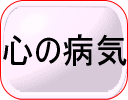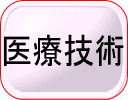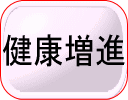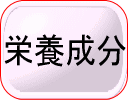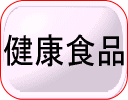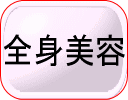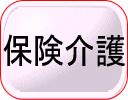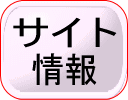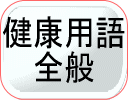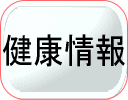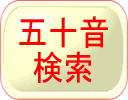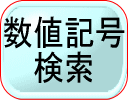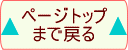|
気管支喘息が特に小児に発症するものは「小児喘息」などと呼ばれることがあります。(小児喘息については別のページで詳細にご説明しています。)
ところで、「喘鳴」とは、「ぜんめい」と読みますが、気管支から生じる「ゼイゼイ」「ゼーゼー」あるいは「ヒューヒュー」する音のことで、狭窄して細くなった気管支を空気が通過するときに出る音のことをいいます。酷くなると聴診器なしでも聞こえるようになります。
通常、人は特に病気でなくても、坂道や階段の昇り降り、強度な仕事などをすると、それなりに呼吸が荒くなり負担を感じます。このような労作時に呼吸困難が生じる「心臓性ぜんそく」や「肺気腫」などの病気があります。
しかし、「気管支喘息」は、これらの状態や病気とは異なり、特別な労作がなくても、「気道が狭くなっている」ために呼吸困難が起こる特徴がある病気です。このように、喘息は「気道の慢性炎症性疾患」ということになります。
喘鳴があったとしても必ずしも喘息というわけではなく、それ以外の病気でも同様な症状を起こすことがあります。たとえば、「慢性気管支炎」「肺気腫」「肺門部のリンパ節腫脹」「縦隔腫瘍」「心不全」および「気管支の異物」などがそれに該当します。
日本での喘息の発症割合は、アトピー型が7割程度、非アトピー型が3割程度とされています。
1998年に日本アレルギー学会より発表された「アレルギー疾患治療ガイドライン」における喘息(気管支喘息)の定義は次のようになています。
|