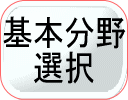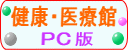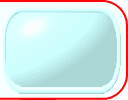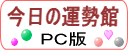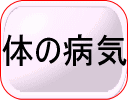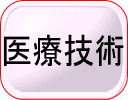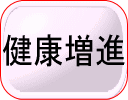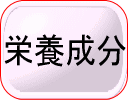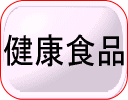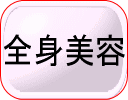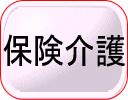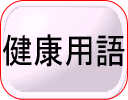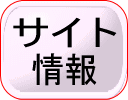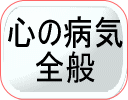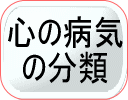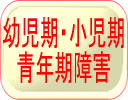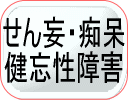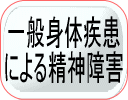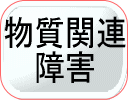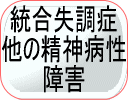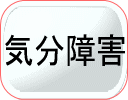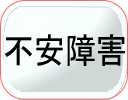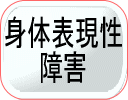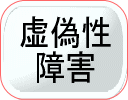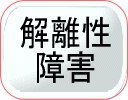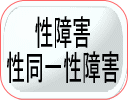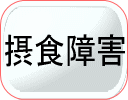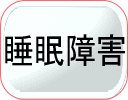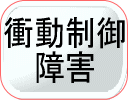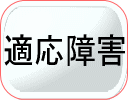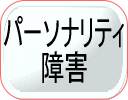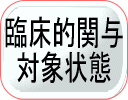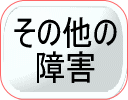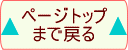|
|
|
|
〔選択性緘黙〕は、特定の生活場面において、会話すべきと期待されているにもかかわらず、言葉によるコミュニケーションを持たない、話そうとせず沈黙を守ることをいい、〔場面緘黙〕や〔選択無言症〕とも呼ばれる〔情緒傷害〕です。 |
|
|
このような〔選択性緘黙〕の発症年齢は5歳以前が多く、全児童の0.2%程度とされます。 |
| 選択性緘黙の型 |
| 第1型 | 積極的依存型で、甘えや攻撃性があります。 |
| 第2型 | 消極的で、甘えや攻撃性は少なく、受動的に依存します。 |
| 第3型 | 甘えはなく、外部からの働きかけに対して攻撃的な反応を示します。 |