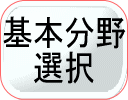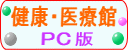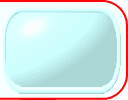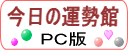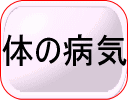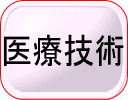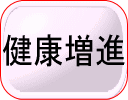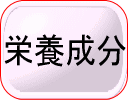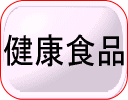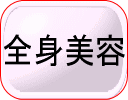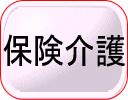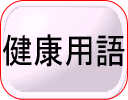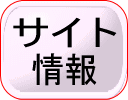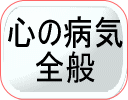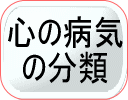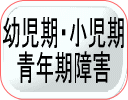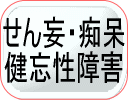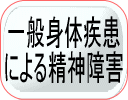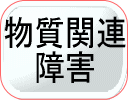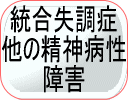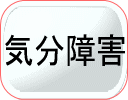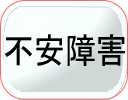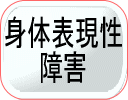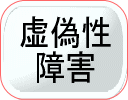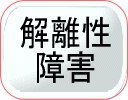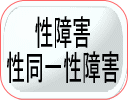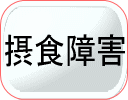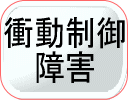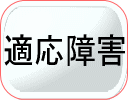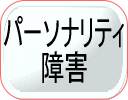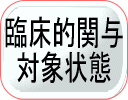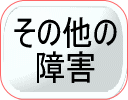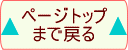|
錯乱性覚醒
|
〔錯乱性覚醒〕は、〔睡眠時随伴症〕のうちの〔覚醒障害〕のひとつです。
一般に睡眠は、「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」とが対になって出現し、これを「睡眠周期」と呼んでいます。このうち、ノンレム睡眠には、熟睡状態である深いノンレム睡眠と、比較的浅いノンレム睡眠とがありますが、深いノンレム睡眠は眠り始めてからの三分の一に出現し、以降はあまり現われません。
通常、睡眠の初期段階では、
「覚醒」→「レム睡眠」→「浅いノンレム睡眠」→「深いノンレム睡眠」
のように睡眠の状態が変化しますが、乳幼児では、深いノンレム睡眠の終りに目覚めてしまう場合があります。このときの脳波は「覚醒相」「レム相」および「熟睡相」が混在した不安定な状態となっていて、目覚めは不完全で中途半端なものとなっています。
多くの場合には、このように目覚めても、またそのまま熟睡状態になるのですが、しばしば不完全な目覚めで錯乱状態になってしまうことも起こり、これを〔錯乱性覚醒〕と呼んでいます。
〔錯乱性覚醒〕に陥ると、乳幼児は呻いたり、寝言をいったり、夜泣きしたり、手足をバタバタさせたりしてぐずります。この症状は数分から長いときは数時間におよぶこともあります。正気に戻った後で、子どもはそのことを記憶していません。
この障害は乳幼児に多く見られるもので成人では極めて稀です。乳幼児の場合、成長と共に自然に出現しなくなるので特に心配はなく治療も必要ありません。
幼児期などでは、睡眠前の習慣として、短い絵本を読んでやったり、お気に入りのぬいぐるみを抱かせてやったり、寝付くまで添い寝をしてやるなどの「入眠儀式」が必要ですが、これを突然止めたりするとよくありません。
就寝時間が毎日異なったり、長すぎる昼寝は避けます。規則正しい生活習慣を身に着けることが大切です。
|
|
睡眠時遊行症
|
〔睡眠時遊行症〕は、〔覚醒障害〕のひとつで、一般的には〔夢遊病〕とか〔夢遊症〕〔夢中遊行〕などと呼ばれています。
〔夢遊病〕は、深い眠りにあるとき、寝返りをうった瞬間など、脳が完全には目覚めていない状態で、急に立ち上がって歩き回ったりするのですが、その症状はせいぜい30秒から長いときで30分程度です。通常は一晩に一度だけしか起こらず、二度も三度も起こることはありません。
本人は非常に深い眠りの状態にあるのですが、目を大きく見開き、言葉を発することもあります。周囲の人が起こそうとしてもなかなか正気にはなりません。しかも、本人はその間のことは全く記憶しておりません。
夢遊病自体を止めることは困難なので、歩き回ったとき転倒して怪我などしないように寝室の周囲に危険物など置かないように気をつけないといけません。また、無理やり正気に戻させようとすると別の心理的問題を起こす恐れもあるので、発作が起こったら静かに寝かせてやるなどするとよいです。
このいわゆる〔夢遊病〕は、5歳くらいの幼児期から12歳ころまでの小学校低学年の子どもの10~15%くらいが経験する障害です。
この〔夢遊病〕の原因は、脳の一部が未発達なために発症すると考えられていて、小学校高学年以降になって、脳が成長を遂げた段階では自然に解消しますから、通常は安心して大丈夫です。
|
|
睡眠時驚愕症
|
〔睡眠時驚愕症〕は、〔覚醒障害〕のひとつで、一般的には〔夜驚症〕とも呼ばれています。睡眠中に突然的に強い恐怖を感じて起き出し、恐怖に対する叫び声や悲鳴をあげたりします。
〔夜驚症〕は、小学校入学前~小学校低学年の児童に多く見られる症状で、男の子の方が多く発症しますが、子どもの15%ほどが経験します。小学校高学年以降では稀になります。また、この障害には遺伝性があるとされます。
通常、〔夜驚症〕の症状は、突然、耳をつんざくような恐怖の金切り声で始まります。本人は突然の強烈な恐怖のために、息が荒くなり、呼吸も速くなり心拍数も上がり、身体を硬直させ汗をかきます。発作時には問いかけても反応はないですが、症状は数分~十数分間で治まります。
悪夢や普通の夢とは異なり、夢の内容などに恐怖を感じるためではなく、どうして怖いのかを本人も理解することができません。突然、強烈な恐怖感が湧き上がりパニック状態になってしまうのです。本当に目覚め正気になったときには、本人は何も記憶していないのが普通です。
睡眠中枢が未成熟な幼少児では、深い睡眠中で脳が覚醒することなしに、恐怖の感情をつかさどっている中枢部が働いてしまうためと考えられています。〔夜驚症〕は、大人でも皆無とはいえませんが、通常は思春期が終わる頃までには、自然に解消するので特に心配はありません。
周囲の人が注意すべき点は、子どもがこのような発作を起こした際に階段から転落したり、窓から飛び出したりしないよう気を配ることです。発作中には、叩いたり、叱ったり、無理やり起こしたりしないことが重要です。
〔錯乱性覚醒〕の場合と同様なのですが、幼児期などでは、睡眠前の習慣として、短い絵本を読んでやったり、お気に入りのぬいぐるみを抱かせてやったり、寝付くまで添い寝をしてやるとよいとされます。また、子どもが強い恐怖を抱くような本やテレビ番組、お化け屋敷などは避けた方がいいです。
多くの場合、特別な治療は不要ですが、思春期を過ぎても発作が起こるような場合には、抗不安薬や、睡眠導入薬を用いた治療が必要かもしれません。
|