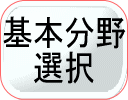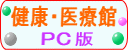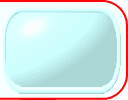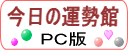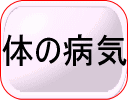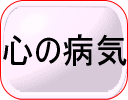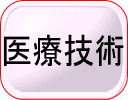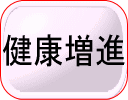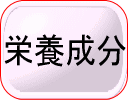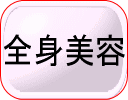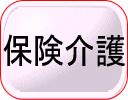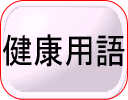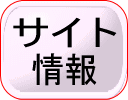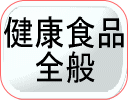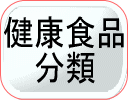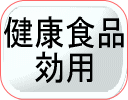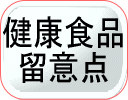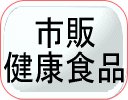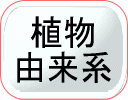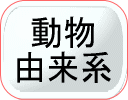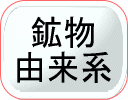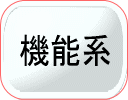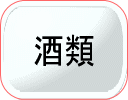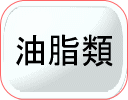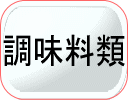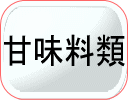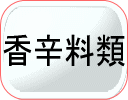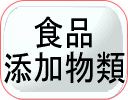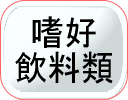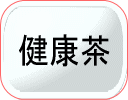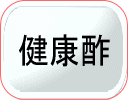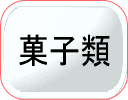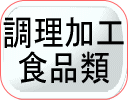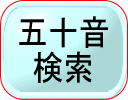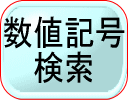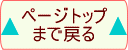|
納豆は、完全食とまでいわれるほど優れた食品ですが、医薬との飲み合わせで問題が起こることがあります。特に、納豆に含まれる納豆キナーゼという成分は、血栓を溶かす力があるとされています。
しかし、一方で、納豆には腸内でビタミンK2を作り出す働きがあります。
このビタミンK2という栄養成分は、実は、怪我などで出血しそうなときに、貴重な血液の体外流出を防げるよう血液を凝固させる成分なのです。
困ったことに、一方では、納豆には納豆キナーゼによる血栓溶解能力があるといいながら、もう一方では、ビタミンK2という成分がその逆の効果を持つという複雑な状況になってしまうのです。
このようなことから、血栓症の予防薬である「ワルファリンカリウム(商品名:ワーファリン)」という薬を服用している人は、納豆の摂取を控えた方がよいとされています。この薬は、抗凝固薬で、血管中に血液の塊である血栓ができるのを防ぐ働きを持つ医薬です。
ワルファリンカリウムを服用している人が納豆を食べると、医薬の治療効果を下げてしまい、血栓症を誘発する危険性があります。
納豆を1週間に2~3回摂取するだけでも、ワルファリンカリウム薬の効果を打ち消してしまうといわれています。この薬の服用者は、納豆を食べたいなら、必ず医師の指示を受けなくてはなりません。
このような問題点を改善するために、ビタミンK2の含有量を減らした納豆も開発されているとのことです。納豆に含まれる納豆キナーゼには、血栓を溶かす作用があるので、ビタミンK2が少ない納豆ができれば安心です。
|