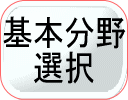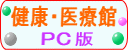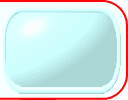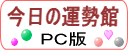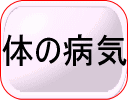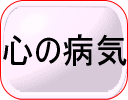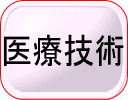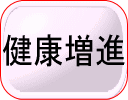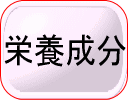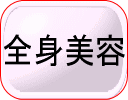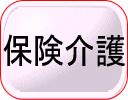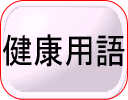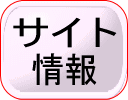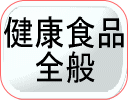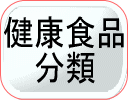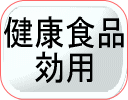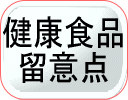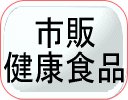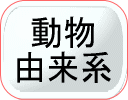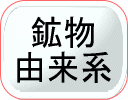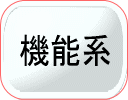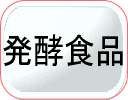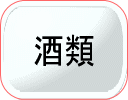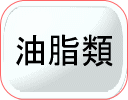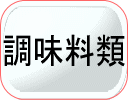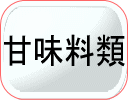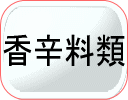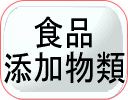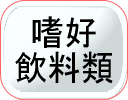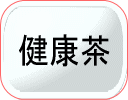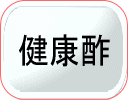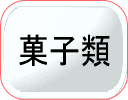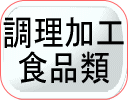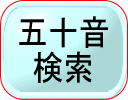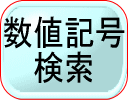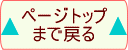|
切干大根(切り干し大根)という言葉は、関東地方での呼び名で、関西以西の地域では「千切大根」と呼ばれる大根の加工法です。また、どの地域でも単に「干し大根」と呼ぶこともあります。
切干大根がいつ頃から食されるようになったのか、その詳細は不明ですが、日本に大根自体が伝来したのは、稲作文化の伝来と同時期ですので、切干大根もほぼ同時期に始まったと想像されます。
日本で大根の栽培が盛んになったのは江戸時代になってからで、品種改良も進み、漬物や切干にしての保存などが盛んになりました。江戸時代には、大根の栽培は飢饉対策としても奨励されていました。
江戸時代の代表的切干大根の産地は、尾張(現在の愛知県)でした。明治以降では、原料の青首大根が宮崎県にも伝わり、同時に切干大根の技術も伝わりました。昭和に入ると、宮崎県が切干大根の最大の生産地となり全国の9割を生産しています。
宮崎県の国富町という地域では、昭和61年に「せんぎり大根生産新興会」というのが発足し、生産農家をはじめ、農協、町、普及センターが力を合わせて、日本一の生産地づくりを目指し現在に至るとのことです。
尚、切干大根の原料としては、青首大根や練馬大根などが多く使われますが、大根の干し方には、千切りにして干した切干と、蒸してから乾燥させた虫干しとがあります。冬の日光と寒風に晒して干した寒干し大根が良いとされています。
|