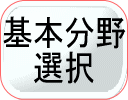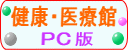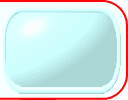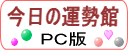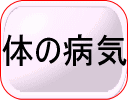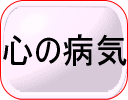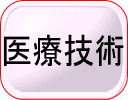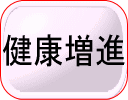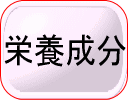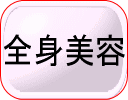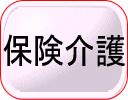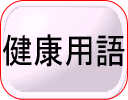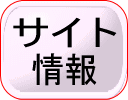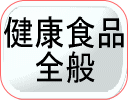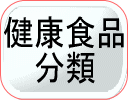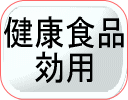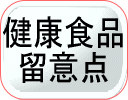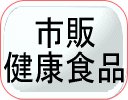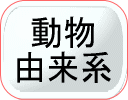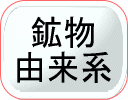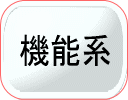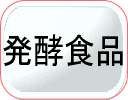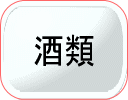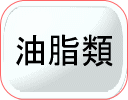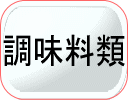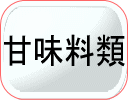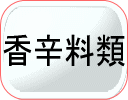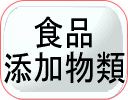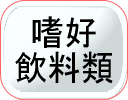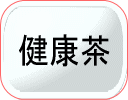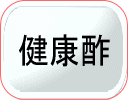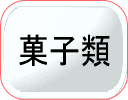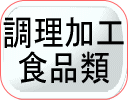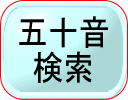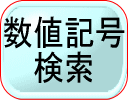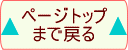|
雑穀米に用いられる穀類には、玄米、大麦、稗(ひえ)、粟(あわ)、黍(きび)、赤米・黒米・緑米、大豆、小豆、黒豆、はと麦、そば米、アマランサス、キヌア、ワイルドライスなど多数あります。
それぞれの穀物は、原産地も異なり、人類が穀物として利用してきた歴史も異なります。また、各穀物に含まれる栄養成分にも違いがあります。
一般に穀類には、エネルギーを生成するために、三大栄養成分として、たんぱく質や脂質、炭水化物が含まれていますが、人の生理機能を調節するためにはビタミン類やミネラル類、食物繊維なども不可欠です。
雑穀米では、いろいろな穀類を混ぜることでバランスよく多くの栄養成分を摂取できるのです。
弥生時代には、臼(うす)と杵(きね)で米をついて玄米として食べていました。土器で炊いたり、こしきで蒸して食べていたようです。平安時代になると、上流階級は白米を食べ、庶民は玄米食を食べるようになりました。
食事回数も室町時代、鎌倉時代には1日二食だったものが、室町時代以降は1日三食に変わっていきました。
江戸時代になると、武士や町民は白米を食べ、農民は米を栽培しますが、自分たちが米を食べるのは正月など特別なときだけで、普段は麦や粟(あわ)、稗(ひえ)などの雑穀を食べていました。
前後になると、食生活が豊かになり、主食は白米となり、雑穀を食べることはほとんどなくなりました。最近になって、雑穀のもつ栄養バランスの良さが認識され、健康食品として人気がでてきました。
|